世界には、たくさんの信念があります。
唯物主義、科学主義、神秘主義、善悪二元論、自然主義はもちろん、宇宙人はいる派・いない派。幽霊はいる派・いない派。地球は丸い派・平面派……などなど、本当にいろいろな信念が存在します。
このように人によって、信じている「真実」は異なります。
でも中には、どれが真実でどれが偽りか悩む人もいると思います。
とくに今の世の中というのは様々な情報に溢れていますから、悩んでしまう人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、私の信念の選び方を書こうかと思います。
個人的なものではありますが、何かの参考になりましたら幸いです。
「正しさ」を重視する現代社会
まず、現代社会の信念の選び方というのは「正しさ」を重視する人が多いのが一般的なのではないでしょうか?
そのために正しさの根拠とするものは、多くは「権威」だと思います。
〇〇大学の教授が言っていたから。〇〇病院の医者が話していたから。国がそう言っていたから。〇〇の研究で論文が出たから。
そういったものを裏付けにしている人は多いのではないでしょうか。
その一方で、権威が信用できないという人もいます。
では、そのような人は何を正しさの根拠とするのでしょうか?
それは多くは、反権威の立場を取る、秘密裏の情報を握るような「信頼できると感じられる人」「誠実と感じられる人」からの情報を根拠とするのではないでしょうか。
他にも、「信頼している〇〇さんがそう言っていた」とか、「有名なYouTuberがそう言っていた」「ファンの有名人がそう言っていた」とか、そういうものを根拠とする人もいますね。
では、そのような正しさの根拠となる対象が、本当に根拠である保証は一体どこにあるでしょうか?
誰がそれを担保してくれるでしょうか?
実は「正しさ」は保証できないものが多い
実は「正しい」と思われるものの多くは、それが本当にそうであると保証してくれるものが存在しないことに、お気付きでしょうか?
テレビで言っていたから。統計で言っていたから。本に書いてあったから。でも、それが正しいと一体誰が照明できるでしょうか?
例えば、「化石があるからティラノサウルスは存在する」という説があります。
- では、その化石をあなたは見ましたか?
- 見たとして、それが本物である保証は?
- それが本物だと裏付ける保証はどこにあるか?
- その保証が本当に正しい保証は?
……と、このように掘り下げていくと、こんなに明白だと思われている「科学的根拠」ですら、実は“信頼”というあいまいなものの上に成り立っていることがわかります。
それどころか、実は、『自身の身あるいは身の回りの事象で確認が取れること』ですら保証になりません。
なぜかというと、自分の身の回りの出来事が本当に世間一般であるという保証がそもそも無いからです。
根本的に、人間には多くのバイアスがあります。
だから、自分が目で見て感じたことすら正確である保証がありません。
じゃあ、バイアスがあるということは、信頼しているつもりの〇〇さんもバイアスを持っているのか? といえば、まったくもって、そのとおりです。それが故意か無意識かは関係ありません。
人間というのは、誰でも、その人自身が見るべき世界しか見ることができません。
ようするに、実際のところ人間社会の「正しさ」というのは、唯一「信頼感」だけで担保されている状態なのです。
つまり、何も間違えていない完ぺきに正しいという状態や保証を得るのは、現代社会であっても、極めて困難であるということです。
では、何が「正しい」のか?
そもそも正しさに自身の芯を望むのは、やめたほうが良いと私は考えています。
先に言ったように、正しさとは原則、保証も証明もできないものです。
このように、掘り下げると曖昧な根拠しか持たないものが「正しさ」の正体なので、正しさというのは、時代、立場、文化、状況によってコロコロと変化します。
だから、根っこにするには本当に不安定なのです。
「正しさ」は十人十色
自身の信念と異なる他者を見た時、誤りであると感じる人が多いと思います。
しかし、先述したとおり、正しさの根拠となりうるものというのは、実際には、権威や信頼という曖昧なもの以外には、とても用意しにくいものばかりです。
それでも、たとえば、1+1=2という計算式が正しいことは誰にでもわかります。
1個のリンゴに、もう1個のリンゴを増やすと、2個になります。
このように、物質的に見て確かめられるものは、間違いないように感じます。
ですが、1個の水素原子に、もう1個の水素原子を足しても、2個の水素原子にはなりません。
このように、条件によっては正しかったものも誤りになってしまうのが、正しさというものの性質なのです。
だから、自身と信念の異なる他者というのは、実際には誤った人ではなく、正確には、あくまでも、異なる立場・異なるものの見方・異なる状況を持つ人であるというだけというわけです。
「正しさ」は結果が証明する?
それでも、結果として出たものは、それこそが「正しさ」じゃないかと考える人も居ると思います。
ですが実際には、同じ結果を見ても、人それぞれ、受け止め方というのは異なってしまうのです。
だから、正しさは信念の基準にしないほうが良いと私は思っています。
それは実際には、とても不安定で儚いものだからです。
信念の選び方
だったら、正しさを杖にできないなら、一体何を杖にすればいいのか?
私は個人的には、以下のように考えています。
自分の人生を体験しているのは誰か?
まず、自分の人生を自分のものとして、見て・感じて・考えているのは、自分自身ですよね。他人ではありません。
自分が怪我したときに痛いのは自分です。つまづいて転ぶのは自分です。自身に楽しいことがあって楽しむのも、自身に悲しいことがあって悲しむのも、最も深刻に思い悩むのも、他人ではなくて自分です。
たまに親切な他者が親身になって、一緒に喜んだり悩んだりしてくれることもあるかもしれませんが、それでも実際にそれを我が身のこととして体験しているのは自分ですよね。
それだけは紛れもなく真実だと思います。これだけは、誰にも覆すことはできませんよね。
自分にとって自分が感じたものは他人が否定しようもなく真実だ
たまに他人の立場なのに否定する人がいるかもしれません。
自分が苦しんでるのを、「そんなの大したことがない」と言ったり、悩んでいるのを、「大した悩みじゃない」と言ったり。
ですが、自分が感じたものというのは、自分にとっては紛れもなく事実です。他者がどう評価しようと変わりません。
それは自分自身にとっての体験であり、自分が今まさに感じている世界に対して具体的な影響を与えているものなのです。
そして自分の人生がどういうものになるかというのは、自分が何を体験したか?何を感じたか?だけが築き上げるものですよね。
いやいや、何が起きたかでしょと思うかもしれないけれども、例えば、同じ「郊外にマンションを買った」という出来事でも、それに満足する人もいれば、もっと都会が良かったと思う人もいれば、一軒家が良かったと思う人もいるし、賃貸が良かったと思う人もいるし、投資用だと考える人も、無駄な買い物と思う人もいる。
つまり、たとえ全く同じ体験をしたとしても、感じ方というのは人それぞれ違うのです。
その感じ方の差はどこで生まれるかというと、価値観です。
だから同じ郊外にマンションを買ったという出来事でも、それが嬉しい体験になる人もいれば、うんざりするような出来事になる人もいる。
ようするに、自分が感じる世界がどんな質を持っているか?を決めるのは、自身の感じ方であるというわけです。
何を体験するかよりも、何を感じるかが人生の質を決める
人間なにが大切か?となると出来事それ自体ではありません。だって、自分が悲しかったり苦しかったりすれば、意味がありませんよね。
たとえば、子供嫌いな人が、周りが幸せだと言っているからって子供を産んでも幸せになれません。
結婚したくない人が、周りが幸せだと言ってるからって結婚しても同じように幸せを感じることはできません。
働きたくない人が、周りが出世は素晴らしいと言ってるからって、出世レースに参加しても、苦しいことばかりになります。
たとえ他者が羨んだとしても、それが自分の望みと異なっていたら、自分の幸せにはなりませんよね。
自分自身が、嬉しいと感じるか?幸せを感じるか?喜びを感じるか?
そこが人生の質にとって、大切ではないでしょうか?
自分が幸福になれるものを信念にしたほうが良い
個人的に思う結論が、これです。
自分が幸せになれるものを信念にした方が良い。
誰かがAが正しいと言っていた。
誰かがBが素晴らしいと言っていた。
このような、世間、権威、第三者、そういう外側にある「正しさ」は、先述したように、実際には、曖昧で不安定です。
外側にある「正しさ」を求めるあまり、自分を不幸にする価値観を、苦しみながら選んではいませんか?
でも、それらは曖昧で不安定だと考えてみると、それを必死に掴み続ける必要性は、あまりないのではないでしょうか。
それよりも、自分の人生に真に影響を及ぼすのは、自身が何を感じながら生きるかしかありません。
それだったら、生きやすい感じ方の中にいられる自分でいたい。
私はそう思っているのです。
🌀今回の記事の要点まとめ
現代社会の傾向
- 「正しさ」は多くの場合、権威によって支えられている。
- しかし、その「正しさ」の根拠も、突き詰めれば非常に曖昧で、保証できないもの。
正しさの限界
- 人の認知にはバイアスがあり、他者も自分も完全には信頼できない。
- 実験や数式でさえ、条件によっては「正しくなくなる」。
だからこそ
- 正しさを求めすぎると、自分の感じ方を無視した不幸な選択をしてしまいがち。
信念の選び方
- 体験の主体である自分自身が、何を「心地よく」「幸せだ」と感じるか。
- 他者の評価よりも、自分の価値観が人生の質を決める。
- 自分が幸せになれるものを信じることが大切。
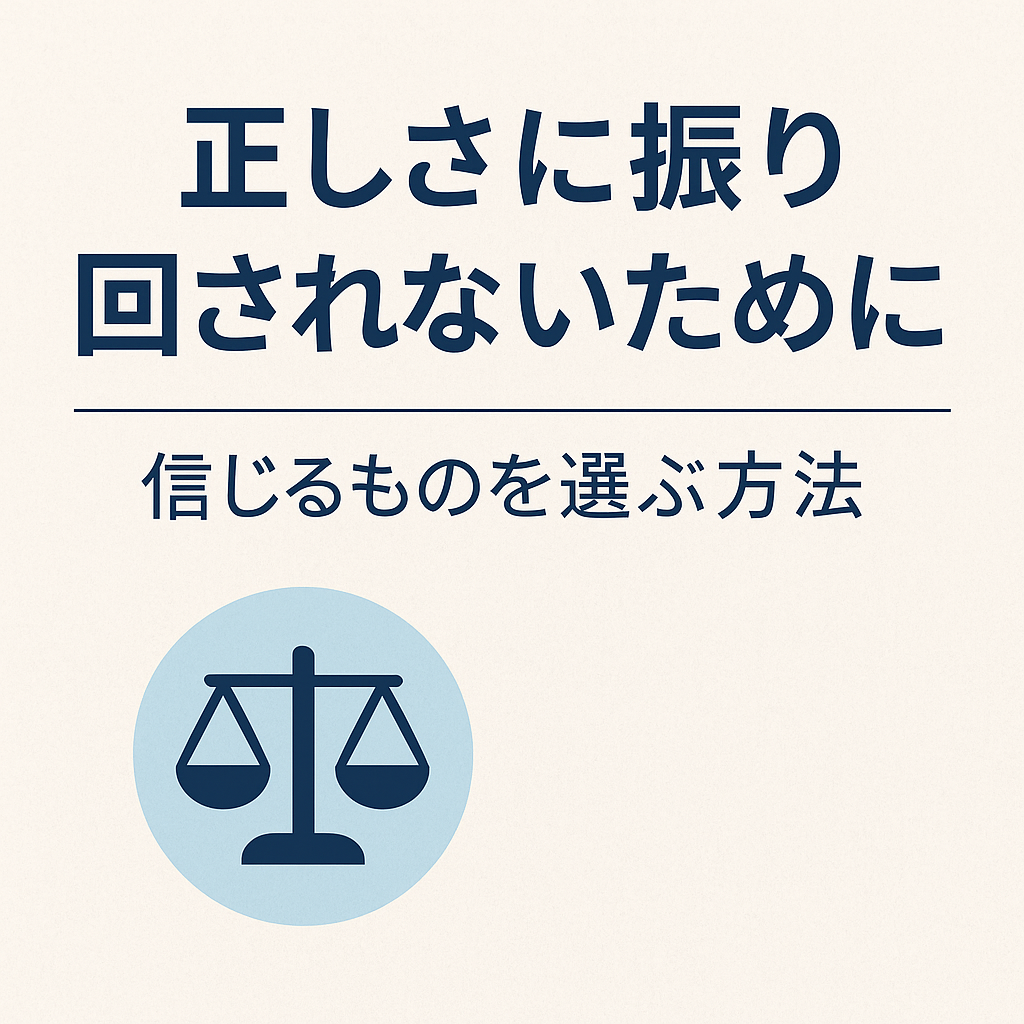
コメントを残す